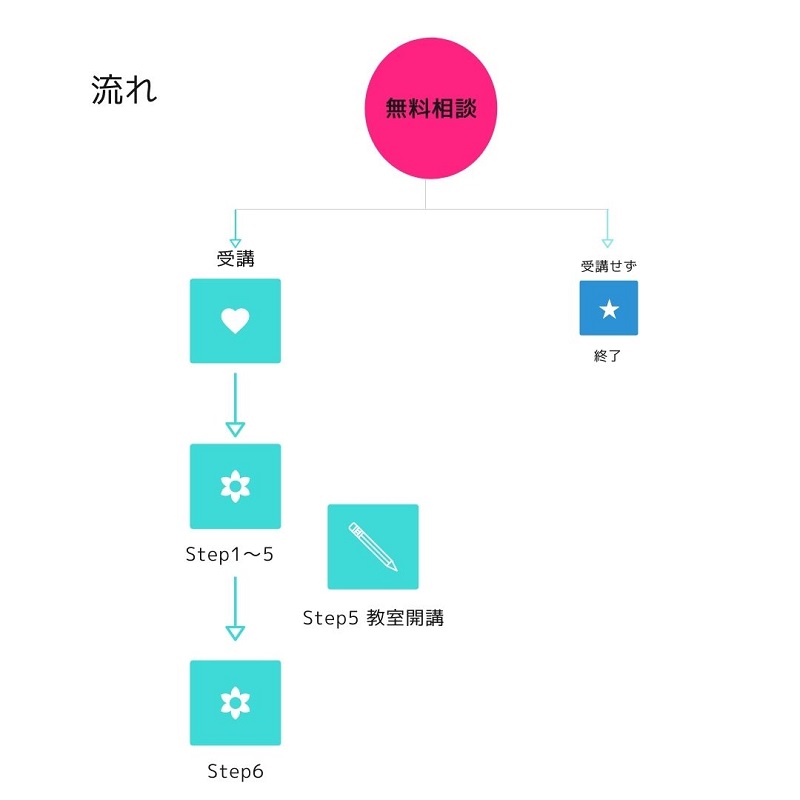ブランディングを加速させるマイキャッチコピーづくりワークショップ
ブランディング・PR加速に必須のキャッチコピー作りを開催します。

概要
本ワークショップは、個人や個人ブランドをより魅力的に映し出すためのキャッチコピーを創出することを目的としています。参加者は、ブランドの核心価値を深く理解し、その魅力を言葉にします。このプロセスを通じて、参加者自身のブランドを見つめ直し、市場での差別化と競争力の強化を目指します。
特色
- 問題解決カードゲームを用いたインタラクティブな学習: 本ワークショップの最大の特徴は、参加者が問題解決カードゲームを使用して、強み・価値観・やりがいを具体的に知る点にあります。ゲームを通じて、楽しみながら創造性を刺激し、他者とのコラボレーションを促します。
- 実践的なキャッチコピー作成ワークショップ: カードゲームで得たインサイトをもとに、実際に自分のブランドやサービス・自分自身のキャッチコピーを作成します。専門のファシリテーターがガイドする中で、効果的なコピーライティングを作成します。ファシリテーターは、参加者のインサイトや言語化されていない自身のこと、隠れた魅力を引き出します。
- ピアレビューとフィードバックセッション: 作成したキャッチコピーは、参加者同士で共有し、構築的なフィードバックを交換します。このプロセスを通じて、参加者は他者の視点を取り入れ、自身のアイデアをさらに磨き上げる機会を得ます。
目的
- 参加者が自身のブランドやサービス・自身の核心価値を明確に理解し、それを言葉にする能力を高める
- インタラクティブなカードゲームを通じて、クリエイティブな思考と問題解決能力を促進する
- ピアレビューを活用して、参加者間での学びを深め、コミュニケーション能力を向上させる
対象者
- 個人ブランド・サービス、自身を確立したい方 -自己PR力を高めたい方
開催概要
■当日の流れ
10時~12時 キャッチコピー作りワークショップ 「カードゲームを通じて自身の魅力・強み・価値観を探る。サービス・ブランドビジョンを明確にする。」
12時~13時 ランチタイム・旬食材ミニセミナー 旬食材研究家・野菜ソムリエプロmiyabi•corps(みやびこーる)主宰荒川雅子先生による旬食材を使ったシーズンフードをお召し上がりいただきます。
13時~14時30分 ピアレビューとフィードバックセッション/キャッチコピー作り
- 日時:2024年6月9日(日) 10時~14時30分
- 場所:work-and-place 芦屋市船戸町5−26マリアキャリーヌビル3階ミーティングルームJR芦屋徒歩3分
- 参加費:15000円(+税)
- 定員:5名まで ※最低参加人数2名
- お申し込み方法:下記フォームよりお申込みください
- 申し込み締め切り日:2024年6月1日(土)
本ワークショップを通じて、参加者は自らのブランディングを一段と加速させ、市場での独自性と競争力を高めるための重要なスキルを獲得することができます
本イベントの特徴:食とのコラボレーション『美味しい時間』
ランチタイムでは、旬食材を使用したフードをお召し上がりいただきます! 旬食材を使用します。身体に良い食事を摂っていただくことで、心身・頭のリフレッシュ・パワーアップを目指します!お楽しみに!
キャンセルポリシー:
お客様によるご予約のキャンセルに際して、以下のポリシーを設けております。ご予約を確定される前に、下記のキャンセルポリシーをご確認いただき、ご了承の上でご予約ください。
3日前:ご予約料金の30%をキャンセル料として頂戴いたします。
当日:ご予約料金の50%をキャンセル料として頂戴いたします。
連絡なしでのキャンセル:ご予約料金の100%をキャンセル料として頂戴いたします。
講師:
「work-and-place」ブランディング担当/国家資格キャリアコンサルタント2級技能士 幟建由佳(ノボリタテ ユカ)
隠れた魅力を引き出すブランディングが得意。強みを最大限に活かし、個々のポテンシャルを輝かせるサポートを提供します。
フード担当:荒川雅子
神戸・芦屋のmiyabi・corps主宰、野菜ソムリエプロ荒川雅子。旬を感じる食生活を専門に座学、オンライン講座を通じて野菜レシピ提案。ホテルや有名店とのコラボレーションイベントも行う。心身を喜ばせる食べ方を追求し、野菜や果物の魅力を広める活動を行なっています。